第4話:みおな先生との出会いと命名
翌朝、ゆうとは緊張と期待を胸にしてあの植物園の自動ドアをくぐった。 受付で短く事情を話すと、やさしい声で案内され、温室の奥にある研究室へと通された。
研究室の扉が開くと、そこに立っていたのは静かな微笑みをたたえた女性だった。 白衣の袖からのぞく指先は清潔で、目元に落ち着いた光があった。
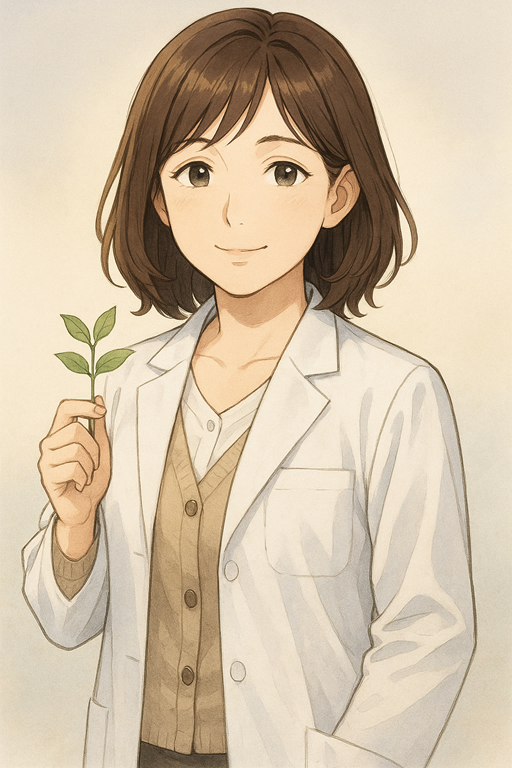
「こんにちは。みおなです。植物のことで相談ということね?」 声は穏やかで、しかし芯のある響きがあった。
ゆうとは深々とお辞儀をして、小さく笑った。 「はい。少し珍しいかもしれないんです。見てもらえますか?」
ゆうとは慎重に容器を取り出した。中には湿らせたペーパータオルで包まれたタネが収まっている。 包みを静かに広げると、ペーパー越しに桜色の粒が、ほんのりと光を透かした。
みおな先生はゆっくりと近づき、タネを間近で観察した。 手に取るのではなく、まずは目と指先で慎重に触診するように見ている。
「……根が出ていますね。やはり、繊細です。乱暴に扱うと折れてしまうこともあるわ」 専門家らしい落ち着いた声で、先生は説明した。
「根が折れたら、元に戻らないんでしょうか?」と、ゆうとは尋ねる。声が少し震えた。
みおな先生は頷いた。 「場合によります。若い根は特に脆い。けれど、適切に扱えば回復することもある。今はまず、乾燥や揺れを避けることが大切ね」
ゆうとは胸の中で深く息を吐いた。 自分がどれほどこの小さな存在を大事に思っているかを、改めて実感した。
「最初に見つけたときから、なんだか特別に感じていて……名前をつけてあげたいんです」 ゆうとの声は控えめだが、真剣さが伝わる。
みおな先生は穏やかに微笑みながら、タネを見つめた。 「名前ね。大切なことだと思うわ。名前があると、育てる側の責任感も変わるもの」
しばらく二人は黙ってタネを見つめた。研究室の外では温室の緑が揺れ、遠くで子どもたちの笑い声が聞こえる。
「どう呼びましょうか?」と、みおな先生がやわらかく促す。
ゆうとは、少し恥ずかしそうに口を開いた。 「えっと……光ったときに、なんとなく『ピカッ』って音が頭に浮かんだんです。で、タネだから……『ピカタネ』って──」 しかし彼はすぐに首をかしげて苦笑した。「でも、ちょっと安直かもしれませんね」
みおな先生は優しく笑って首を傾げた。 「言葉の響きは大事よ。『ピカタネ』も愛らしいけれど、少し音が子どもっぽい気もするわね」
ゆうとが考え込んで目を閉じた瞬間、タネがふっと明るく光を強めた。まるで「どうだろう?」とでも言うように。
ゆうとはその光を見てはっとした。顔をあげ、静かに言った。 「じゃあ……『ヒカッタネ』っていうのはどうでしょうか。光る=ヒカッ。タネ=タネ。響きも素直で、可愛いと思います」
みおな先生の目がやわらかく細まり、微笑が深くなる。 「ヒカッタネね……」彼女は口に出して確かめるように繰り返した。「いい名前ね。あなたが見つけて、そして大事に連れてきた名前だもの」
「これからは、進化があるたびに見せに来なさい」とみおな先生が付け加えた。 「一緒に経過を見て、名前もそのときの姿にふさわしいものを考えましょう」
ゆうとは満面の笑みで頷いた。 「はい。必ず見せに来ます。ヒカッタネ、これからよろしくね」
ヒカッタネは、ふんわりと安定した光を灯した。 その光は、ただの光以上の意味を持っているように見えた——誰かに愛され、守られる名前を得た確かな瞬間だった。
(注:ここでは初回の命名を行いました。今後の進化や成長のたびに、ゆうとがみおな先生に報告し、名前を検討していく流れになります。)
見えないところで起きている成長に気づくこと。 そして、不安なときは一人で抱え込まず、信頼できる知識や専門家に頼ること。 資産形成でも、数字が動かない時期こそ焦らず、正しい情報に立ち返る姿勢が大切です。